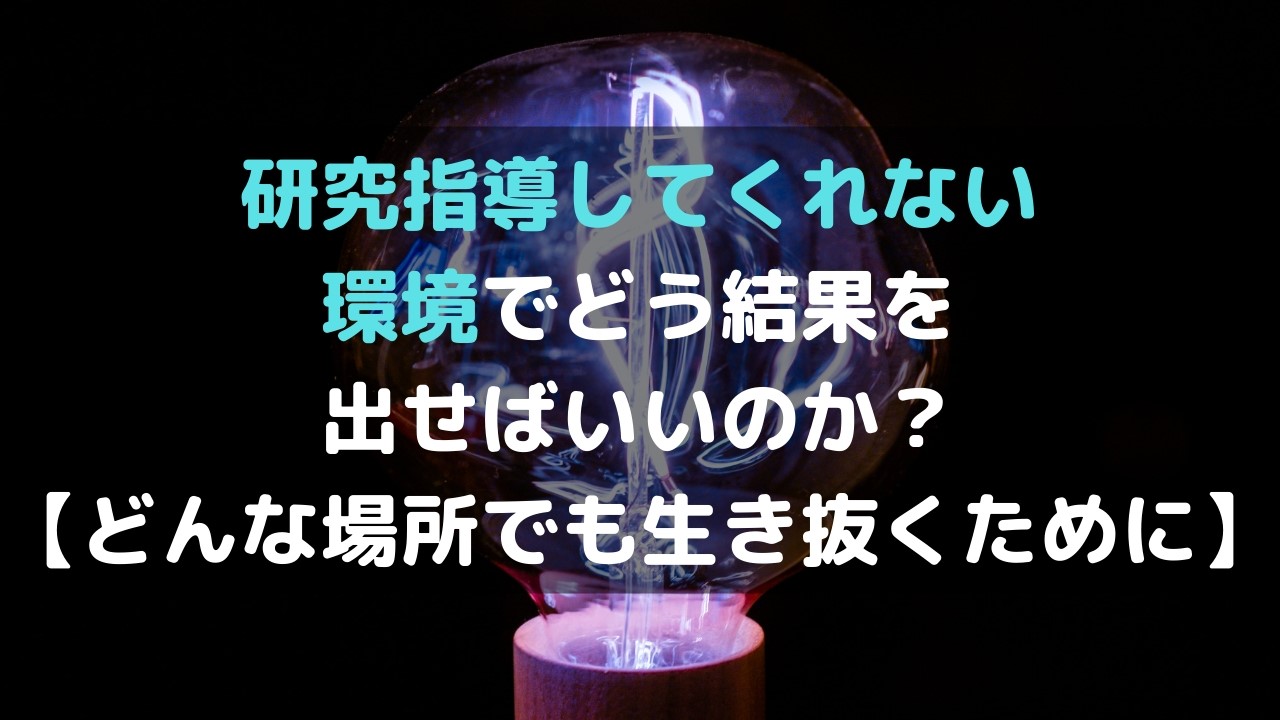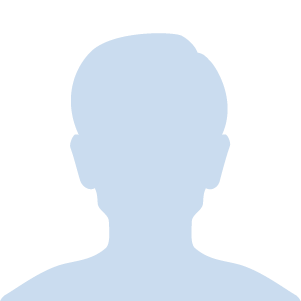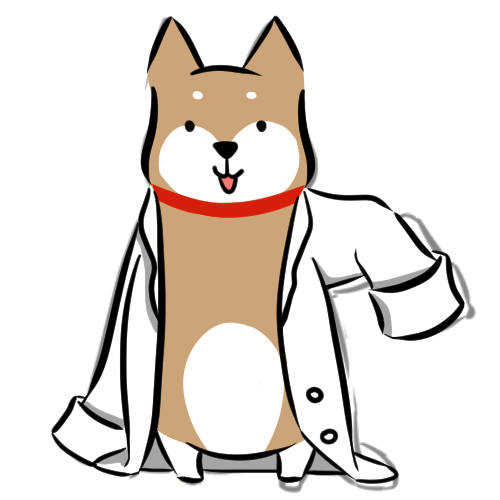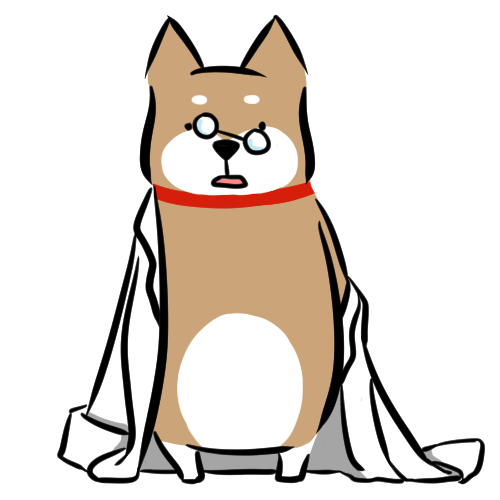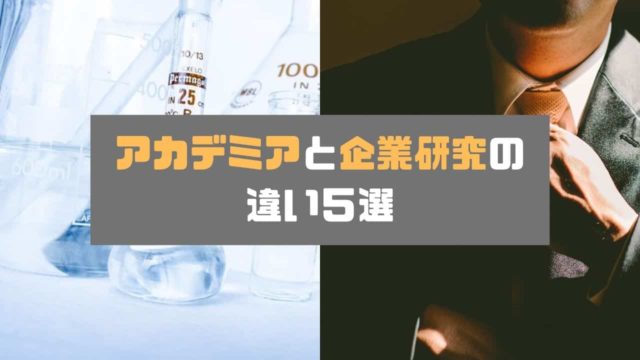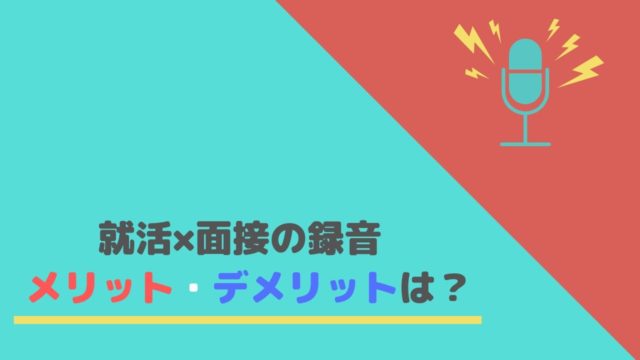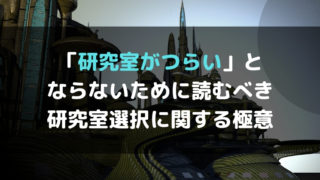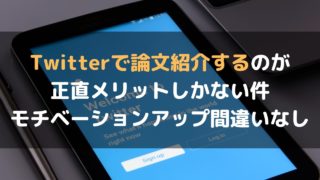配属された研究室では指導してくれる雰囲気がまるでないのですがどうしたら良いですか?
指導してくれない研究室とかブラックですよね?
当記事では上記の疑問にお答えします。
本記事の内容
- 研究指導してくれない環境で結果を出すために大事な思考
- 指導してくれない環境でも成果を挙げるのが研究者としての仕事
修士で大学を卒業後、企業で研究をしているくりぷとバイオ(@cryptobiotech)と申します。
研究室時代に「指導を期待していると人生詰む」と悟ったことがあります。
当記事では「研究で指導を期待するのは是か非か?」ということについて論じます。
結論からズバッと言ってしまうと、指導を期待している人は成功しません。
研究の指導をしてくれない環境下でも、しっかりと成果を出せる研究者はいます。
なぜ指導がなくても成果が出せるのか?
これまでに様々な研究者を見てきて、ある程度の共通点が見えてきたので当記事ではそれを説明しますね。
当記事は数分で読めますし、研究室で日々実験しているB4~M2の学生さんには特に威力を発揮する記事だと自負しますっ。
どうぞご覧ください。
目次
研究指導してくれない環境で結果を出すために大事な思考
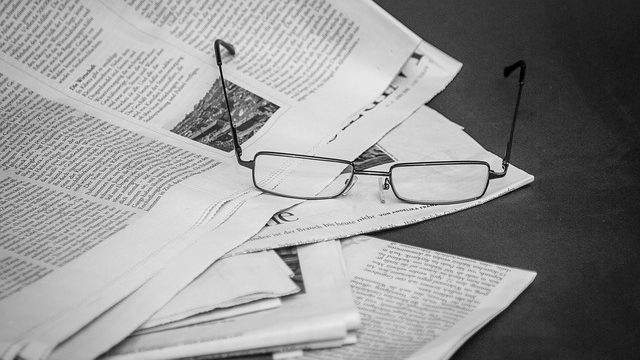
研究の指導をしてくれない環境下でも成果を出し続けるために必要な思考は以下の通りです。
- 「研究指導してくれない」という考え方を捨てる
- 研究指導してくれない環境で先輩がどう立ち振る舞っているを知る
- 研究で大事なのは「指導してくれない」と嘆くことではなく「指導させる」こと
- 指導してくれないから全部1人でやるという発想は地獄に落ちる
- リカバリーを何個か用意して精神的に安定をはかる
1つずつ説明していきますね。
「研究指導してくれない」という考え方を捨てる

なぜやめるべきかというと、「指導してくれない」という思考はあなたを「指示待ち人間」に変えるからです。
誤解を恐れずに言いますが、研究において指示待ち人間は最悪です。
そもそも研究はたくさん失敗するのが前提で、指示されたことをやったのにうまくいかないなんて日常茶飯事。
でも指示待ち人間はその日常茶飯事に対して「教授・先輩の指導力がないからだ」とか文句言い始めたりするんですよね…。
研究は「指導してくれないなら自分でやるか」と開き直ることがけっこう重要で、自立心がかなり求められます。
学部4年生はまだ指導を求めても良いと思いますが、修士に上がってまだその思考を持ってたら要注意です!
研究指導してくれない環境で先輩がどう立ち振る舞っているのかを知る


「研究の指導をしてくれないとか最低の環境だ!」
と思っている方は、先輩や卒業したOBの業績を一度調べてみるのがおすすめです。
どんな環境や組織であれ、自分よりも目上の人がどのように立ち振る舞っているのかを常に観察し続けるのは超大事です。
観察だけでなく「なんで先輩は指導がなくても成果出せるんですか?」ってダイレクトに聞いてしまうのも良いですね。
指導してくれないことに嘆くのって、結局のところ「自分が成果を出せるか不安だから」なんですよね。
指導がなくても成果を出せる事実を知っていれば焦る必要もない。
「指導してくれない」と嘆くあなたは、一度冷静になって周りを見回してみましょう!
スポンサードリンク
研究で大事なのは「指導してくれない」と嘆くことではなく「指導させる」こと


指導してくれない環境で成果を出すために大事な思考は、「教授や先輩に指導させること」です。
「指導してくれるのを待つ」のではなく「相手から指導させるように仕向ける」のが正解。
例えば、あなたが担当しているテーマでどうしても進め方がわからなくなった時に“自分から”相談したりなどですね。
指導を待っていてもその機会が到来することはほとんどないので、自分から機会を創りだすのが重要。
当然ですが教授や先輩にも忙しい時はあるので、忙しい時に相談しても「ごめん、後で良い?」となります。
また、質問する時の準備が全然足りてなかった場合も、先輩や教授は受け付けてくれない可能性が高い。
なお目上の人に相談するときに抑えておきたいポイントは以下の通り。
- 教授や先輩がデスクワークをしているタイミングで声かける
- これから何を相談するかを最初に語る(結論が一番先)
- この相談が何分くらいかかるか最初に伝える
- なぜそれを相談したのか理由を説明する
- 困っていることに対して自分なりの対策法を伝える
挙げるときりがないですが、最低限必要かなと思うことは上記の通りですね。
ここらへんを明確にしてから相談すると、教授や先輩もかなりの高確率で相談に乗ってくれるのでお試しあれ!
周りが指導してくれない環境は、自分の取り組み次第で変えられますよ!
指導してくれないから全部1人でやるという発想は地獄に落ちる


指導してくれない環境でもやっていくと意志を固めた人が注意すべきは「全部1人で進める」と決意しないこと。
研究を1人で進めるのは相当な修羅の道です。
なぜなら本来あなたがやらなくても良い作業なども、全て自分がやらないといけなくなるから。
バッファー作製とか細胞継代とか、誰かに任せることができる作業は詳細プロトコルを作って作業移管していくべき。
例えば細胞継代を自分でやるのに30分かかるとします。
バイオ系で細胞扱っている方ならわかると思いますが、週に2回継代する必要があるので、週に1時間かかっています。
単純計算で年間48時間くらい使ってますね。
48時間あれば論文が何本読めることか…。
1本1時間で読んだとしたら48報読めるので、細胞継代を作業移管できるだけで、新規テーマが1個創れるかもしれません。
このように「自分がやらなくても良いこと」を見極めてラボアシスタントや派遣社員の方に移管していく思考は超大事。
「指導してくれないから自分でやる」は正義ですが、「自分で“全部”やる」は地獄に落ちるので周りに頼りましょうね。


リカバリーを何個か用意して精神的に安定をはかる


研究の指導をしてくれない環境がどうしても嫌なら、万が一の可能性を考えた行動をとるのもおすすめです。
研究室時代の僕は考えていなかったことですが、今となって「真剣にやっておけば良かった」と思ったのは以下の通り。
- ブログや投資などで“収入面の不安”を解消する
もうこれに尽きます。
ブログや投資は絶対に、時間的にも体力的にも余力がある学生時代に手を付けておくべき。
僕は両方とも社会人になってから始めたのですが、本業との両立は正直かなり大変です笑
学生の頃からブログや投資を始めてある程度の収益を上げるレベルまで到達しておくと、精神的に相当安心できます。
かなりぶっちゃけた話ですが、収入面で安心できると、ヒトはなぜか色々なことに挑戦できるようになります。
僕もブログや投資を始めてそれなりにお金を稼げるようになった今、「あ、別に会社クビになってもやっていけるな」と思ってきました。
思い切って挑戦して成功する→成果も出てポストも獲得して収入も安定する
ができれば一番望ましいのですが、今の研究界隈ではそんなうまくいく話でもないです。
ブログや投資で最低限やっていけるお金を稼ぐ→精神的に安定する→思い切って挑戦する→成果が出る
という研究者の形があって良いのかなあと最近は強く思っています。
研究の指導をしてくれない環境で成果を出したいというあなたは、まず収入面で精神的な安定を獲得するのがおすすめですね。
スポンサードリンク
指導してくれない環境でも成果を挙げるのが研究者としての仕事


というわけで「指導してくれない環境を嘆いても意味がない」的な話をしました。
むしろあなたがそう思っているということは、世間の理系学生もあなたと同じことを思っている可能性が高いです。
それってよくよく考えると差をつけるチャンスなんですよね。
指導されなくてもやっていけると決意して、周りと協力する思考を持つまでが早ければ早いほど研究に没頭できる時間は伸びます。
どんな環境でも成果を継続的に出し続けるのが研究者のあるべき姿だと思うので、ぜひあなたも自立心を獲得しましょう!
指導されない環境で自分を成長させることができたら、どんな環境でもやっていけるようになりますよ。
というわけで当記事は以上です。
当記事が参考になったら、ぜひくりぷとバイオ(@cryptobiotech)のTwitterもフォローしてやってくださいませ。
ではではっ