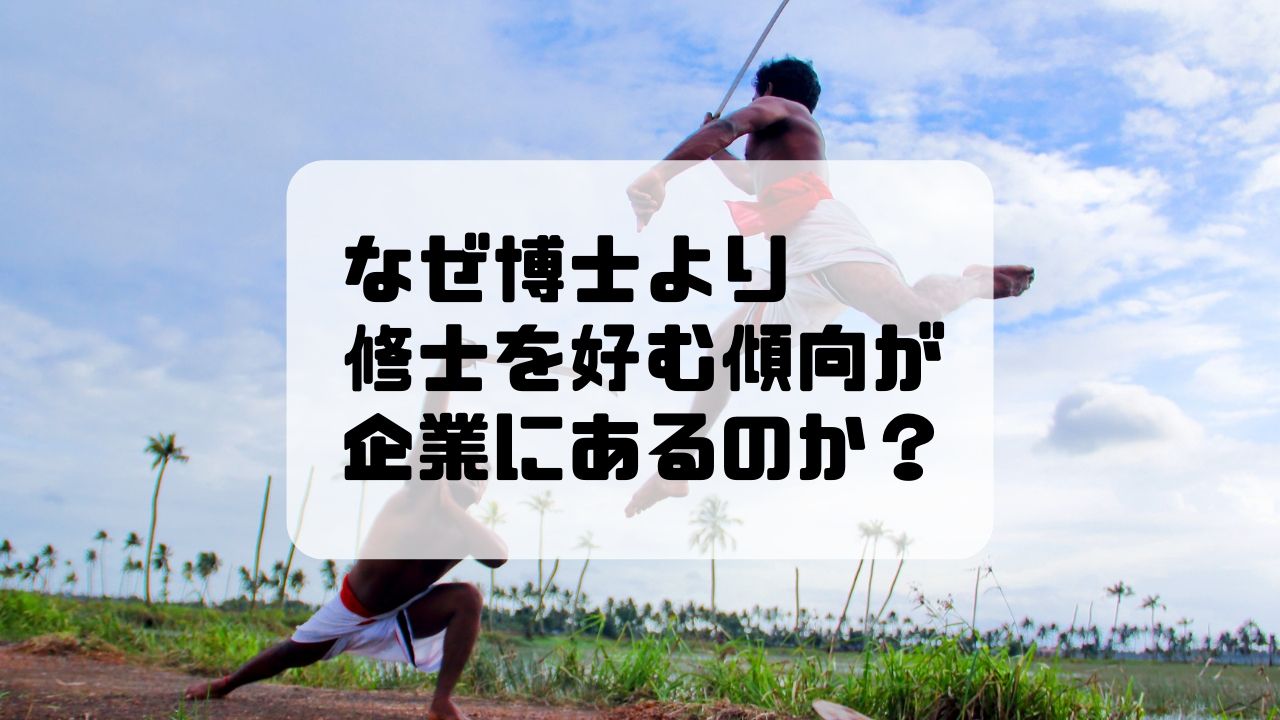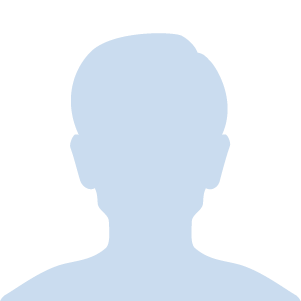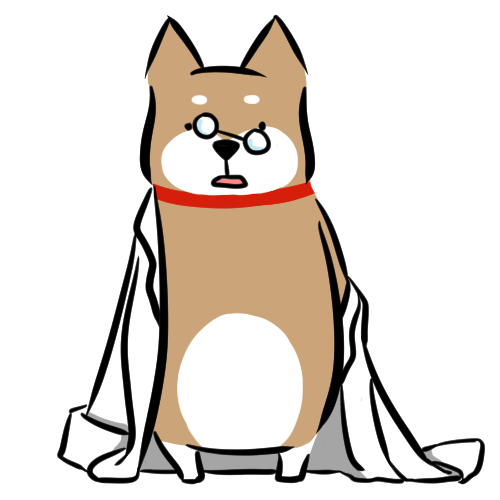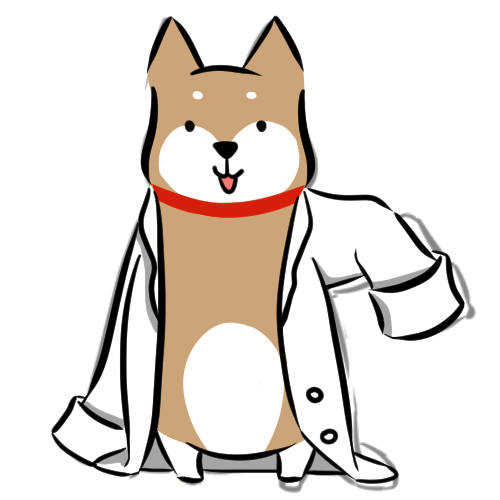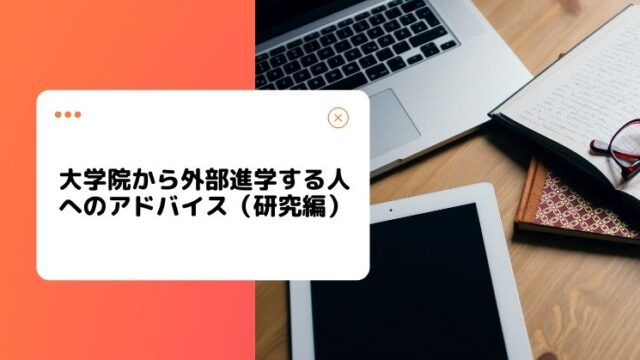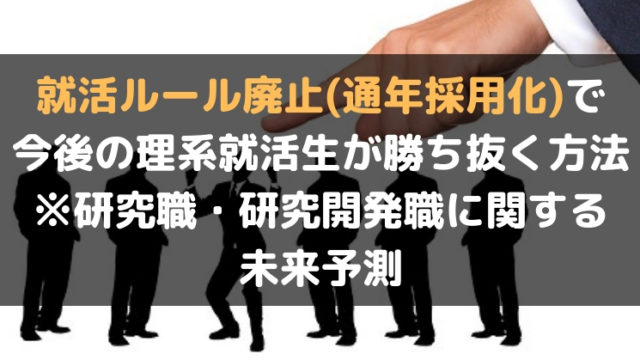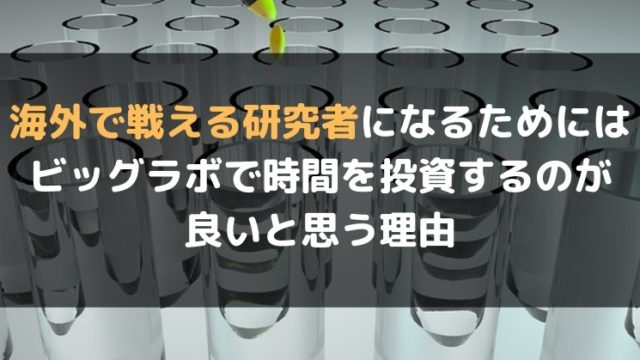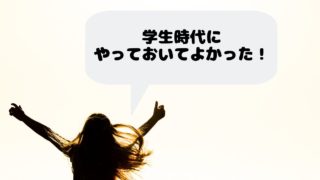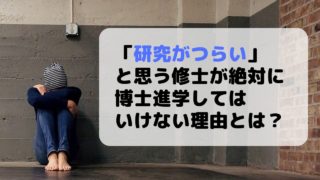日本企業は「博士よりも修士の方が採用しやすい」と思っているようだけどなぜ?
博士でも企業の内定をバンバン獲れる人いるし、一概にそれが正しいとは思えないけど。
実際に修士卒の企業人から見た意見が聞きたいです。
当記事では上記の疑問・ご要望にお応えします。
本記事の内容
- 【大前提】修士でも博士でも優秀な人材はどこ行っても通用します
- 企業が博士卒より修士卒を好みやすい理由の考察
- 修士でも博士でも“過去のこだわり”を捨てられない人は使えない
修士課程で大学を卒業後、大手企業で研究しているくりぷとバイオ(@cryptobiotech)と申します。
幸いにも就活では製薬・食品など様々な企業から研究職・研究開発職の内定をいただくことができました。
先日、以下の質問を頂いたのでもう少し掘り下げてみようと思います。
修士卒の方がいいと思われる理由は、おっしゃる通り博士卒だとミスマッチ率が高くなるからかと。
あと僕の後輩でも博士持ちの方がいますが、研究に対するこだわりは良くも悪くも非常に強・・・
続きは質問箱へ#peing #質問箱 https://t.co/nLhoUX3eSU— くりぷとバイオ@研究職 (@cryptobiotech) June 19, 2019
博士は修士より研究の就職が厳しいという見解、むしろ博士までいったほうがいいという見解…どの情報が自分に適切かよくわからないです。
修士までがいいと言われるのは、あまりに自分の研究の専門性が高くなりすぎると採用側とのミスマッチ率が高くなるからですか?
でもそもそも研究はアイデアが重要なのだから、なるべく広く知見しておくものじゃないんですかね…。
くりぷとバイオさんから見て、なぜ修士卒がいいという意見が出るのだと思いますか?
結論をぶっちゃけると「修士の方が企業から好まれる風潮」は間違いなくあると思います。
ただしそれは「修士の方が博士よりも優秀」というわけではありません。
当記事ではその部分を深く掘り下げてみますね。
実際に修士卒で就職して働いている人間の意見なので、企業が修士卒を好みやすい理由を知りたいあなたにもお役に立つかと。
数分で読めるので是非ともどうぞ!
目次
【大前提】修士でも博士でも優秀な人材はどこ行っても通用します


まず最初に大前提をお話しておきます。
修士卒でも博士卒でも、優秀な人材はどこの世界に飛び込んでも通用します。
修士卒でバリバリ研究できる人もいるし、博士卒なのに全然研究できない人も普通にいます。
当然、修士卒で研究が全然できない人や、博士卒で化け物のように研究できる人もいます。
「修士だから研究では優秀じゃない」とか「博士だから研究では優秀」とか、一方的な決めつけで語るのは不毛です。
その議論に決着つくことは永遠にないので。
この前提をご理解いただいた上で、なぜ企業は修士卒を採用する傾向にあるのか?を解説しますね。
スポンサードリンク
企業が博士卒より修士卒を好みやすい理由の考察


実際に修士卒の立場で企業を数年経験して「なるほど、博士卒が採用されにくいのはこれか」と思った理由は以下の通りです。
- 良くも悪くも博士は修士より“研究”に対する思い入れが強すぎるから
- 博士卒は企業とのミスマッチが致命的になりやすいから
- 博士卒は企業で3年経験した修士卒を超えていないと厳しいから
1つずつ説明していきますね。
良くも悪くも博士は修士より“研究”に対する思い入れが強すぎるから


良くも悪くも博士卒の人は“研究”に対する思い入れが強すぎます。
もちろん学部4年から博士3年までの6年間を研究に捧げてきた自負があるはずなので、その感覚は至極当然です。
ですが企業は「ぜひ研究をやってくれ!」と思って博士を採用するわけじゃないんですよね。
「その研究力を活かして当社でぜひ“新しい製品”を創ってくれ!」と思って採用するんですよ。
この企業側の事情を把握せずに就活に臨む博士課程の学生は非常に多い。
僕の大学同期(修士卒研究職)から聞いた話ですが、博士卒の新入社員が研究職ではなく開発職に配属され、1~2か月で辞めたそうです。
「自分は研究職に配属されると思っていた。開発は自分のやりたいことじゃない」と言って去っていったとのこと。
一方、僕もそうですが「研究職じゃなくても別に良いかな」という思考の持ち主が修士卒には多いです。
なぜなら僕らは「博士卒の人に研究では及ばない」と思っているから。
だからこそ修士卒は「自分の強み(専門性)を創りたい」という想いが強く、それゆえ柔軟に色々な経験をしようと思うんですよね。
この“柔軟性”こそが博士卒の方に欠けている要素なのかなと、企業を数年経験して感じました。
「研究オンリーの思考を持つ博士」は企業から避けられると考えます。
博士卒は企業とのミスマッチが致命的になりやすいから


博士は修士と違い、就活では「実績」と「専門性」がとても重要視されます。
博士採用では「実績がある」かつ「企業の事業領域と合っている」学生が求められると言っても過言ではありません。
ただここで問題になるのは「企業の事業領域と合っている」という点。
例えば全合成を専門とする博士課程の学生が、ガチガチのバイオ系メーカー(発酵とか)に内定を獲るのは至難の業です。
しかも企業の事業領域と合っている研究をしていたとしても、その事業領域で募集人数が「ゼロ」だったら意味がありません。
博士課程は実績×専門性マッチングだけでなく、時代のトレンドも考慮する必要があります。
どんなに成果を出していても、明らかにトレンドから外れた研究をしていると採用に至らないこともある。
一方で、修士課程の学生は専門性をあまり重視されない傾向があるので、分野が違うメーカーで採用に至るケースもあります。
「専門性が違う学生を採用して企業で育成するなら修士の方が良い」と思っている企業はけっこうあると思いますね。
専門性がなくてもミスマッチしても採用される修士とは異なり、専門性とマッチングが(ほぼ)必須の博士を企業が採用しにくいのはしょうがないのかなとも感じます。
博士はもちろん、これから博士課程に進学しようと思っている修士もこの点はしっかりと意識すべきですね。


博士卒は企業で3年経験した修士卒を超えていないと厳しいから


企業が博士卒を採用しにくい理由は、「その企業で3年経験した修士卒の社員」と比較してどれだけ優れているかを判断しにくいから。
例えば修士卒で研究職に配属された社員は、3年間かけてその担当事業領域の知識を習熟させると共に、社内の繋がりも構築します。
3年間かけて企業の雰囲気を掴んだ行動ができるようになるだけでなく「ビジネス感覚」も相当磨かれます。
修士卒が博士卒に“研究”で勝てないのと同様、博士卒は3年間企業を経験した修士卒に“ビジネス感覚”で勝つのは困難です。
博士課程の学生はこの事実を受け入れたうえで「でも自分はその3年目社員より○○という点で優れている」と言えないといけません。
もちろん“研究”は一つ挙げられるかもしれませんが、“研究だけ”で攻めるなら圧倒的な業績を残すくらいじゃないとアピール対象にはならない。
“研究”が全てに優先する企業などこの世界に存在しないので、ビジネス感覚を3年積んだ社員をどう蹴散らすかを博士は全力で考えるべき。
「私は研究ができます」は前提条件なので、研究+αの強みを語れない限り企業側は博士課程学生を獲ることはないでしょう。
スポンサードリンク
修士でも博士でも“過去のこだわり”を捨てられない人は使えない


というわけで「なぜ企業が博士よりも修士を採用する傾向があるのか?」について、経験に基づいて考察してみました。
ただ再度強調しますが「博士だからダメ」というわけではないです。
企業に入ってから様々な人を見てきましたが、結局は「過去にこだわって前に進めない人」がダメというだけです。
修士でも博士でも「研究しかやりたくない!」という人は企業では使えない。
自分の価値観や実績を簡単にポイッと捨てて新領域に飛び込める人は、どの職種の人でも優秀。
日本企業はこれからどう転ぶのか誰にも予測できないゆえに、企業が過去の成功にこだわらない人を求めるのは自明でしょう。
例えばですが、僕が尊敬するtabeさん(@mac_immunol )のような考えをもつ博士課程学生が増えることを期待します。
博士に進んだからと言って、研究「職」に拘る必要は全くなくて。
自分の人生や社会、そして所属組織における課題を「研究」出来る人材として活躍できればそれで良いと思います。— tabe@創薬研究/博士就活ブログ (@tabe_phdcareer) April 21, 2019
というわけで当記事は以上です。
当記事が参考になったら、ぜひくりぷとバイオ(@cryptobiotech)のTwitterもフォローしてやってくださいませ。
ではではっ
>>「成功企業に潜むビジネスモデルのルール」をもう一度見てみる