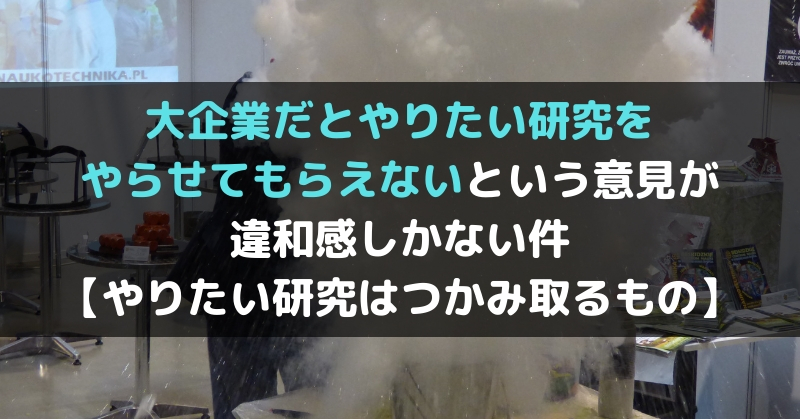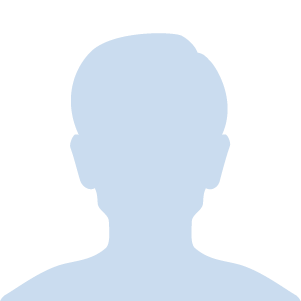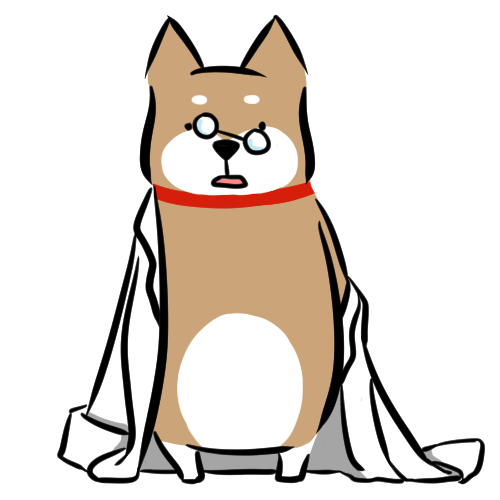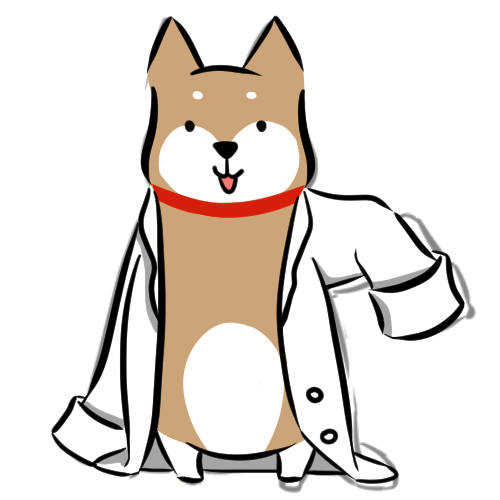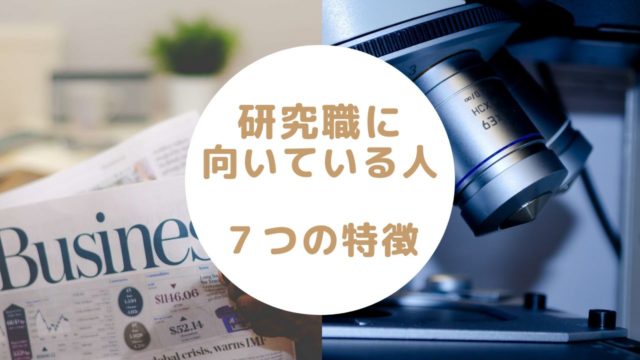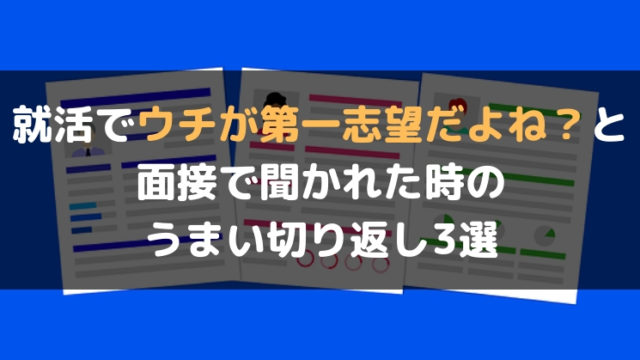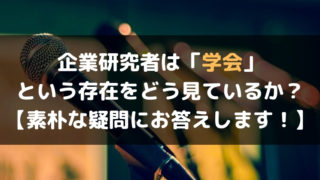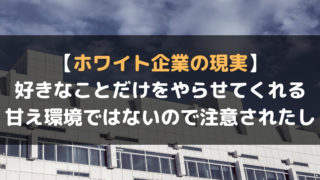大企業だとやりたい研究をやらせてもらえないって本当ですか?
どこの企業なら自分のやりたい研究ができるのでしょうか?
やりたい研究をやるためにベンチャーに行った方が良いのでしょうか?
当記事では上記の疑問にお答えします。
本記事の内容
- そもそもあなたは今「やりたい研究」をやっているのか?
- 大企業でもやりたい研究をやるためのコツ【少しずつバス停を動かす理論】
- やりたい研究をやるためにベンチャーを選ぶのが危険な理由
- 大企業でもベンチャーでもやりたい研究はつかみ取るもの
こんにちは、くりぷとバイオ(@cryptobiotech)です。
本業として企業で研究をしながら、趣味としてブログや投資に勤しんでおります。
「大手企業の研究職だと自分のやりたい研究ができないってよく聞くんですが、実際どうなんですか?」という質問をOB訪問などでよく聞かれる。
逆に、就活生さんが今やっている研究は「自分が本当にやりたいと思った研究」なんでしょうか…
やりたい研究は与えられるものではなく、創り出すものでは。
当記事では上記ツイートを深堀りしてみようと思います。
僕も就活時には「やりたい研究ができそうな企業」を選んでおりましたので、あなたがそう考える気持ちもよくわかります。
やりたくない研究しかできない企業に入っても楽しくないですよね。
が、実際に「やりたいことができそうな企業」に入社を果たした僕が最初に与えられたテーマは全然やりたくないテーマでした。
その時は「このテーマでやっていけるかな…」とかなり不安になったことを覚えています。
ただ入社して数年が経った今、最初からやりたい研究テーマができるわけないかと悟り、その悟りのおかげか逆に今ではやりたいテーマができています。
結論として「大企業でもやりたい研究テーマはできる。ただし段階を踏む必要がある」と確信しました。
当記事ではそのあたりを中心に「大企業でもやりたい研究テーマをやるコツ」や「ベンチャーならやりたい研究ができるという勘違い」に関しても解説します。
当記事は3~4分でサクッと読めますし、読んだ後は「やりたい研究テーマを推進するのに必要なこと」がわかるはずです。
目次
そもそもあなたは今「やりたい研究」をやっているのか?

「大企業ではやりたい研究ができないって聞くけど本当ですか?」
とOB訪問で聞いてくる就活生さんには、必ず僕はこのように答えています。
では、○○さんは今「本当にやりたい研究」ができているのですか?
この質問をすると、大体は下記の3パターンに回答が分かれます。(多い順です)
- やりたい研究が今できていないから、企業ではやりたい研究がしたいんです!
- 最初はやりたい研究ではなかったけど、徐々に楽しくなってきました!
- そもそもやりたい研究って何でしょう…?(悟りを開いた目で)
残念ながら3番は僕の方から何かコメントできることがないので、1番目と2番目に焦点を向けます。
まず2番目の回答から。
これは非常に的を得ていると感じておりまして、何事も「やってみてしばらく経ってからようやく面白さがわかる」と僕自身も考えています。
僕も最初に与えられたテーマは全く予想だにしていなかったテーマで、ノー知識だったので不安しかありませんでした。
ただそのテーマの背景を色々調べていくうちに「あれ、意外に自分のやりたいこととリンクしているやん」となり、そこからテーマが楽しくなっていきました。
やりたくなかったテーマが「やりたいテーマ」に変わることはよくあります。
それゆえ2番目の回答をする就活生は「きっとこの就活生はどこの企業でもやっていけるな」といつも感じてます。
要するに「何かアドバイスせずとも自分でやりたい研究をやれる人」と思える就活生ですね。
一方で、1番目の回答をする就活生。
これはどこの企業にいっても「やりたい研究」ができない危険性があります。
なぜなら企業に入っても僕のように「やりたい研究テーマを与えられない」可能性があるから。
研究者というものはすべからく「“自分が”やりたいと思っている研究で世の中を変えたい」と思っています。
世の中には「あなたのために、あなたのやりたいテーマを上に通して、あなたのやりたいことを全部やらせてあげる」という善人はいません。
むしろ皆、自分がやりたいテーマをあなたに手伝ってもらいたいのです。
自分がやりたいテーマで世の中を変えるために。
それゆえ「やりたいテーマをやらせてもらえない」と受け身に考えている時点で、一生やりたいテーマがやれない可能性があります。
やりたい研究テーマをやるには、自分で練りに練って、誰もが納得できるレベルに仕上げて、諦めずに提案し続けないとやれません。
やりたい研究をやるために越えなければならないハードルは、想像以上に高いです。
スポンサードリンク
大企業でもやりたい研究をやるためのコツ【少しずつバス停を動かす理論】


とはいえ「世の中そんなに甘くないぞ!」とドヤ顔で語るだけでは、あなたにとって面白くもなんともないですよね。
ですので本項では大企業でもやりたいテーマをやるためのコツを説明します。
やりたい研究テーマをやるために必要だと考えることは以下の3つです。
- 与えられたテーマでまずは結果を出す
- 上長にやりたいテーマを何度も何度も小出しで提案する
- 与えられたテーマに加えて少しずつ自分のやりたいテーマを動かしていく
順々に説明しますね。
与えられたテーマにまずは全力を尽くす


まず大企業でやりたい研究を与えるための一歩として、与えられたテーマに全力を尽くしましょう。
企業は営利組織ですので、新人として入ってきたあなたに、あなたのやりたいテーマをやらせるボランティア精神はありません。
自分の言葉に「信頼」を付与するためにも、まずは与えられたテーマをこなすのが大事です。
もちろん研究なので、結果としてうまくいかないこともあるでしょう。
ただしその与えられたテーマに対して全力で取り組んでいる姿勢を見せるのが重要です。
例えばテーマの最先端論文を業務後に読んで、部署の関係者に共有するといった行動も必要になるかと。
新人から「やりたいテーマ」をやらせてもらうと考えるのはかなり危険な思考なので、1~2年は与えられたテーマに全力を尽くすべし。
上長にやりたいテーマを何度も何度も小出しで提案する

与えられたテーマに精一杯取り組んで、ある程度周りから認められるようになってきたら、やりたいテーマを上長に小出ししていきましょう。
個人的には、仕事の時よりも飲み会の場などで小出ししていくのが良いのかなと。
なぜ小出しにしていくのが良いかと言うと、いきなりガッツリ提案書出しても、上長からしたら読む気がしないからです。
頑張って30枚くらいのスライドを作って提案すれば努力は認められるかもしれません。
が、多分「すまない、とりあえず会話ベースで良いから簡単に説明してくれないか」と言われる可能性が高い。
そうなるとせっかく頑張って作ったあなたのスライドと時間が無駄になります。
それゆえ飲み会などのフランクな場で「○○みたいなことをしたいのですが」と聞くのがGOOD。
上長は「なぜそれをやる必要があるのか?」とか「どれくらいで、どうやってやるんだ?」など聞いてくれます。
多分最初はある程度話していくと論破される瞬間が来ます。
が、その論破される瞬間が来たらもうけもの。
論破された部分の情報を飲み会後に調べて、また再提案すればOK。
そうすれば多分また違うところで論破されて、その情報をまた追加していく…。
この繰り返しが結局のところ有効かなと思っておりまして、要は「上長を相談役(≒味方)にしてしまうこと」が重要。
あなたがやりたいテーマをやらしてもらうには、それなりの時間が必要になります。
それに心が折れてしまう程度の「やりたい」であれば、そもそもやっても無駄なのかなと。
どうしてもやりたいテーマなら、否定を退け、粘り強く提案し続けましょう!


与えられたテーマに加えて少しずつ自分のやりたいテーマを動かしていく


頑張って提案してもどうしてもやりたいテーマができない!と悩んでいるあなた。
おすすめしたいのは与えられたテーマをやりながら、少しずつ自分のやりたいテーマを動かしていくことです。
例えば僕の知り合いの話で恐縮ですが、与えられたテーマにあまり興味がない時、そのテーマを進めながらがっつり別の闇実験もする人がいます。
で、闇実験が当たった場合、与えられたテーマはほどほどに終了させます。
「○○と▽▽を検討したけどダメだったので、ちょっとこのテーマは厳しいです」的な。
そして「では次にどんなテーマをやるつもりなんだ?」と聞かれたら、上長に闇実験の内容を話すという流れ。
強欲の極みですね(真顔
これを僕は「バス停を少しずつ自宅に動かしていく理論」と呼んでます。
自宅の近くにあるバス停のブロックを1日1cmずつ動かしていくと、1年間で3~4mだけバス停が自宅に近づくという理論。
それを続けていくと、なんといつの日か自宅前がバス停になるという最高の結果に!
日々の業務とは別に、自分のやりたいテーマを少しずつトライしていくという行動は、一見無駄なことをしているようにも思えます。
しかし企業からしてみたら「とりあえずまずは成果出せ」という感じなので、成果が出ているのであれば意外に許されたりします。
ただ闇実験をやっているということは業務+αの作業量をしているということなので、ある意味「努力が報われた」とみることもできます。
そう考えるとやはり「周りの人がやっていないこと」をやる人に、結局は勝利の女神がほほ笑むのかなと。
やりたい研究ができない…と嘆く人は、本当にやりたいことをやるための行動を取れているのか再考してみましょう。
やりたいことは、強い意志さえあれば基本的にやれます。
やりたい研究をやるためにベンチャーを選ぶのが危険な理由
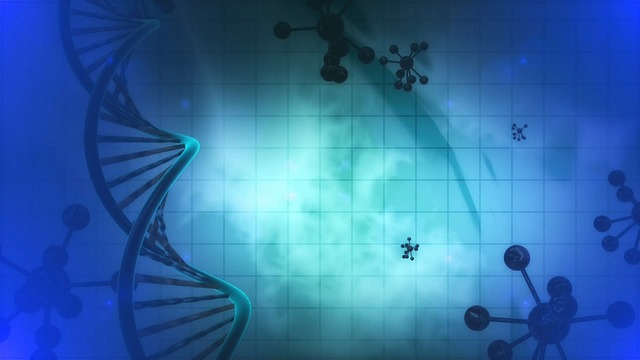
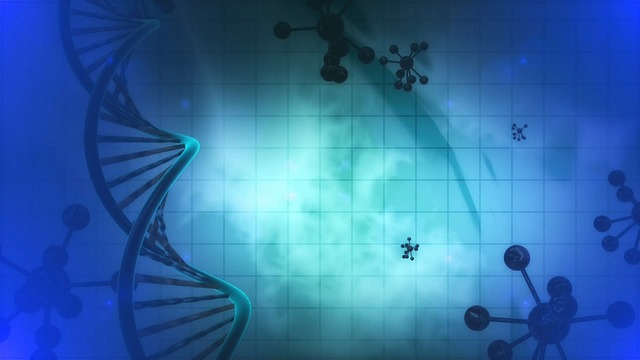
というわけで大企業でもやりたい研究をやるために必要なことを解説しました。
当記事ではもう1つ「ベンチャー企業ならやりたいことができるのか」に関しても簡単に説明しようかなと。
個人的な意見ですが、結論としてはベンチャー企業でも大して大企業と変わりません。
なぜなら結局サラリーマンとして雇われている以上、雇い主の要求に応えることが大前提だからです。
最初は研究バリバリやれていたとしても、業績が傾けば「研究している場合じゃない!」となるリスクもありますよね。
「自分とマッチすると思うベンチャー企業でバリバリやるぞ!」と思って入社したのに、結局やりたいこと以上に別の雑務が多く辞めた人を知っています。
前項でご説明した通り、自分がやりたい研究をするためにはそれなりの準備と覚悟が必要です。
働く環境さえ変われば自分はやりたい研究ができるようになる、というのは少々危険な考え方だと思いますね。
大企業でもベンチャー企業でも、まずは「信頼を築く」のが最優先。
その後にようやく「テーマ提案の交渉機会を得る」という流れなので、信頼構築をすっ飛ばさないようにしましょう。
スポンサードリンク
大企業でもベンチャーでもやりたい研究はつかみ取るもの
というわけで当記事は以上です。
どの企業に属していようとも、自分のやりたいテーマをいかに「当社でやる意義ありますよね!」と思ってもらうかが大事。
そう思ってもらうには社内事情を把握する、上長の好みも把握する、周りからの協力も得るために動きまくる、批判にも折れない心を持つなどなど。
ただ研究だけをやれば良いってわけではないのが企業研究者。
自分の想いを一方通行で主張してもあまり受け入れてもらえません。
やりたい研究をやらせてもらえない…。
と嘆く暇があるなら、論文を一本でも多く読んで情報を集めましょう。
やりたいことをやるためにあなたに用意された時間は有限です。
やりたいことをやれる企業を選ぶよりも、入った企業でやりたいことをやるために周りを巻き込むのが最強と考える今日この頃です。
やりたいことは自分でつかみ取りましょう!
当記事が参考になったら、ぜひくりぷとバイオ(@cryptobiotech)のTwitterもフォローしてやってくださいませ。
ではではっ